ステーブルコインは導入が進むか?〜JPYCが第2種資金移動業者に

仮想通貨は少し持っていますが、事実上決済に使えない。使うたびに税金かかりますしね。当面は、投機として持っておくくらいしかありません。だいぶ値上がりはしていますしね。税制整備待ち。
デジタル円を政府が発行して、決済手数料ゼロの世界を作って欲しいなあ、と思うのですが、なかなか国が実現するのは難しいのでしょうかね。
そんな中気になるニュースが。実際に日本円と連動するステーブルコインがそろそろ動き出しそうです。値上がりを期待するものではなく、実際にビジネス上の決済手数料を抑えられるようになれば、中小企業の飲食店や小売・サービス店でも導入したくなると思います。
PayPayに強力な対抗馬? 日本円連動ステーブルコイン「JPYC」を金融庁が認可、今秋始動
https://japan.cnet.com/article/35236850
PayPayの対抗馬というのもあるかもしれませんが、金融機関全般、クレカ会社全般に対する対抗馬担ってほしいですね。クレカ業界は、VISAやMasterCardに支配されており、日本のデジタル赤字が進む要因のひとつになっています。中小店舗は決済手数料の高額化に悩んでいるので、まだクレカよりは決済手数料の安いPayPayを使っているお店が多いのだと思います。決済手数料0の世界を期待しています。
なのでJPYCの現状を調べてみました。
JPYCの概要(発行主体・仕組み・使われ方)
JPYC(JPY Coin)は、日本円と価値が連動するステーブルコインです。1JPYC=1円となるよう設計・運用されており、ビットコインなど一般的な暗号資産に比べ価格変動リスクが極めて小さいことが特徴です。発行主体はJPYC株式会社(旧:日本暗号資産市場株式会社、2019年設立)で、同社が2021年1月に日本初のERC-20準拠の円建てデジタルトークンとしてJPYCの発行を開始しました。
JPYCは資金決済法上の「前払式支払手段」として位置付けられています。暗号資産(仮想通貨)ではなく、プリペイドカードのように事前にチャージして支払に使うデジタル通貨という法的扱いです。この分類によりJPYC発行体にはユーザー保護の義務など一定の規制が課されており、法的枠組みの下で運営されることで信頼性向上にもつながっています。
もっとも、2023年の法改正で「ステーブルコイン」が新たに電子決済手段(資金移動業型のデジタルマネー)として定義されたため、JPYC株式会社は2025年に資金移動業者として登録を完了し、JPYCを正式な電子決済手段として発行できる見通しです。2025年秋には金融庁承認のもと、日本初の円建てステーブルコインが正式発行される予定であり、これによりJPYCは発行者による1円での償還(買い戻し)が保証される「真のステーブルコイン」として展開される見込みです。
真のステーブルコインですか。なるほど。今現在の現金は、ほとんど金融機関に預けられており、データでやり取りすることで決済できるわけですが、毎度手数料がかかる。振込だけで、数百円とられるとか、非常に運用コストが高いです。ステーブルコインがこの現状を変えていけるとよいのですが。
JPYCの仕組み
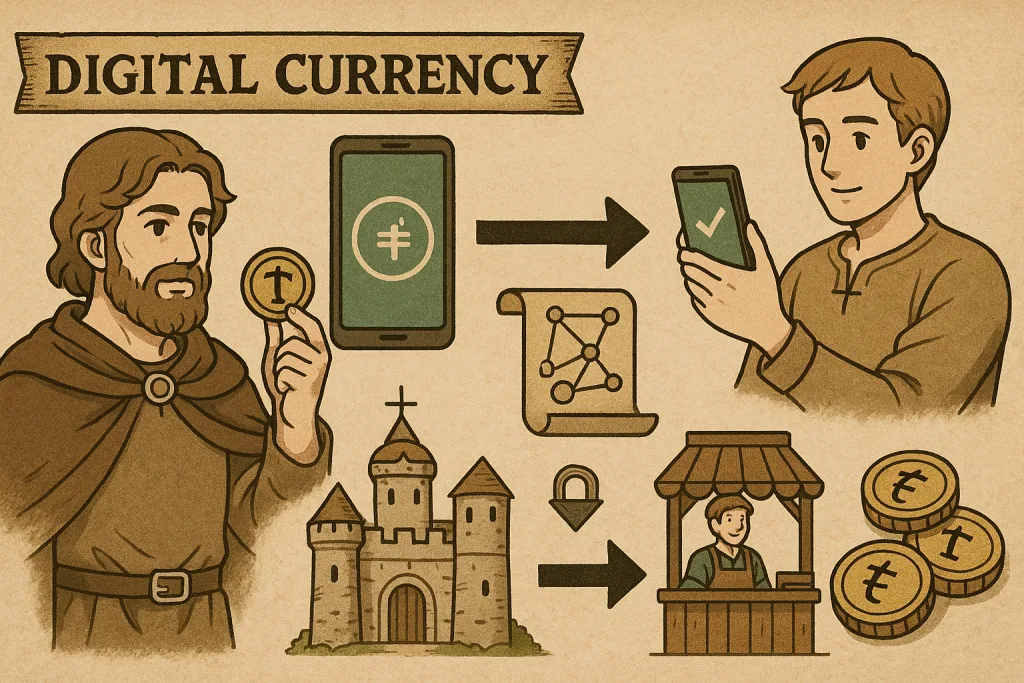
仕組み: JPYCは公的な裏付け資産によって価値が維持されています。JPYC株式会社はユーザーからの申込み後に受け取った日本円に応じてJPYCトークンを発行し、ユーザーのデジタルウォレットへ1JPYC=1円のレートで自動配布します。裏付け資産としては、受け取った資金が銀行預金や日本国債などで適切に保全されており、JPYCの価値の安定性を支えています。実際、JPYC Prepaid(現行の前払式JPYC)の場合、発行元が常に1JPYC=1円で販売・提供しているため市場価格が大きく乖離しにくく、公式サイト上でも1円相当で購入できるギフト券等に交換できるサービスを提供することで、二次市場でも極端に1円を下回らないよう担保されています。今後発行予定の新たなJPYC(資金移動業型)は、発行体による1円での償還保証が付くことで、より確実に価格が1円に維持される見込みです。
技術基盤としては、 JPYCはイーサリアムをはじめ、PolygonやAvalanche、Astarといった複数のパブリックブロックチェーン上で発行・管理されています。誰でも取引履歴を検証できるオープンな分散台帳上に存在するため透明性が高く、発行量や移転履歴を誰でも確認できます。また複数チェーンに対応していることで、ユーザーは用途に応じて取引速度や手数料が最適なネットワークを選択できる柔軟性があります(例:Ethereumメインネットはセキュリティが高い反面ガス代が高く、Polygon等のL2は手数料が安価)。JPYCトークン自体はERC-20互換トークンであり、対応ウォレット(MetaMask等)で管理・送受信できます。
今後はどのように使われていくのか?
JPYCは「デジタル円」として様々な用途が想定されています。個人間の送金やオンライン決済はもちろん、日常の買い物にも使えるよう設計されています。もっとも現時点ではJPYC決済を直接導入している店舗は限定的であるため、多くの場合ギフト券との交換を介した利用が行われています。例えばJPYCをVisaプリペイドカードのデジタル版「Vプリカギフト」やデジタルギフト券「giftee Box」に交換することで、Visa加盟店でのオンライン決済や各種ECサイトでの買い物にJPYCを間接的に充当できます。JPYC公式サイト上で交換機能が提供されており、ユーザーは保有JPYCを使ってAmazonギフト券やQUOカードPayなどにチャージし、それらを従来通り決済に使うという形で実質的にJPYCで日常の決済を行うことが可能です。
2021年~2022年には、百貨店の松屋銀座でJPYCを使った商品の購入実証も行われました。このケースでは、顧客がJPYCで支払った金額相当の商品をJPYC社が店舗から代理購入し、後日受け渡すというスキームで、国内初のリアル店舗におけるJPYC活用例として注目されました。そのほか、ふるさと納税(地方自治体への寄付)の支払いにJPYCを活用する試みや、JPYCを他社ポイントや電子マネーに交換する提携も進んでおり(例:QUOカードPayへの交換機能実装)、デジタル決済手段としてJPYCを現実経済で使うための橋渡しが拡大しています。
JPYCのメリデメ
BitCoinなどの暗号資産と比べて価格変動がなく、実際に決済ができる点が(できるようになる点)がメリットですかね。BitCoinも少し持っていますが、ビックカメラで買い物に使えるものの、BitCoinが値上がりしているため、購入のたび、税金がかかることになります。はやくJPYCで買い物してみたい。そして何より、店舗側の手数料がかからなければ、今のように「手数料が嫌だからキャッシュレス止めました!」って店がでなくなることでしょうかね。
デメリットは・・・なんだろ。まだ法整備の不明瞭なところと、実際に店舗で決済するとなるとどういった物理的な手段が用意されていくのか、不明確なところでしょうか。スマホのアプリで簡単に決済とかはいいのですが、店舗側でのレジとの連動など課題もまだまだありそうですね。
中小企業店舗がJPYCを導入する場合の対応ポイント
まだ中小企業には早いのでしょうが、いずれ導入する時期が来ることを期待しています。

導入に必要な機器やシステム
最低限必要なのはインターネット接続端末とデジタルウォレットです。具体的には、スマートフォンやタブレット、PCなどにJPYC対応のウォレットアプリ(例えばMetaMaskやJPYC社推奨のウォレット等)をインストールし、店舗用のJPYC受取アドレス(口座)を用意します。クレジットカード決済のように専用のカードリーダー端末や電話回線は不要で、QRコードなどを使った決済にも対応可能です。店舗側は自分のウォレットアドレスをQRコード化して提示し、顧客にJPYCを送金してもらうだけで支払いを受け付けられます。ブロックチェーン上でトランザクション承認が完了すれば入金確認となり、ウォレットアプリの画面で受取履歴をチェックできます。
MetaMaskつくってみましたが、パソコンを新しくしたら、アクセスできなくなってしまいましたw 1万円相当を入れていたはずなので、ちょっと再度アクセスしてみようと思います。できるかしら。
このように加盟店契約や決済代行会社による管理が不要な点はJPYC導入のハードルを大きく下げます。誰でもウォレットを用意すればネットショップや実店舗で自由にJPYC決済を受け付けられ、売上の回収も即時に行えます。将来的には、POSレジや会計ソフトとブロックチェーンウォレットを連携させるソリューションも登場すると予想されますが、現状ではまずスマホ1台から手軽に始められるのがメリットです。初期コストも端末代程度(既存の端末を使えば実質0円)であり、新たな決済端末をリースしたりする必要もありません。
なお、店舗がJPYCを受け取った後に日本円へ交換したい場合には、JPYCを暗号資産交換業者(取引所)やJPYC発行体に送って換金する手続きが別途必要です。2025年以降はJPYC社からの償還が可能になる見込みですが、現時点ではJPYCを取り扱う取引所(例:ZaifやCoinTradeなど※)で売却し銀行振込で出金する方法などが考えられます。もっとも換金せずとも、前述のようにJPYCを各種ギフト券や他の電子マネーに交換して店舗の経費支払い等に充当することも可能です。運用方針に応じて、JPYCのまま保有するか円転するかを決めるとよいでしょう。
そんなところで。

