AI議事録スタートアップ「オルツ」がorz 〜売上の9割が循環取引で水増しされたものだった
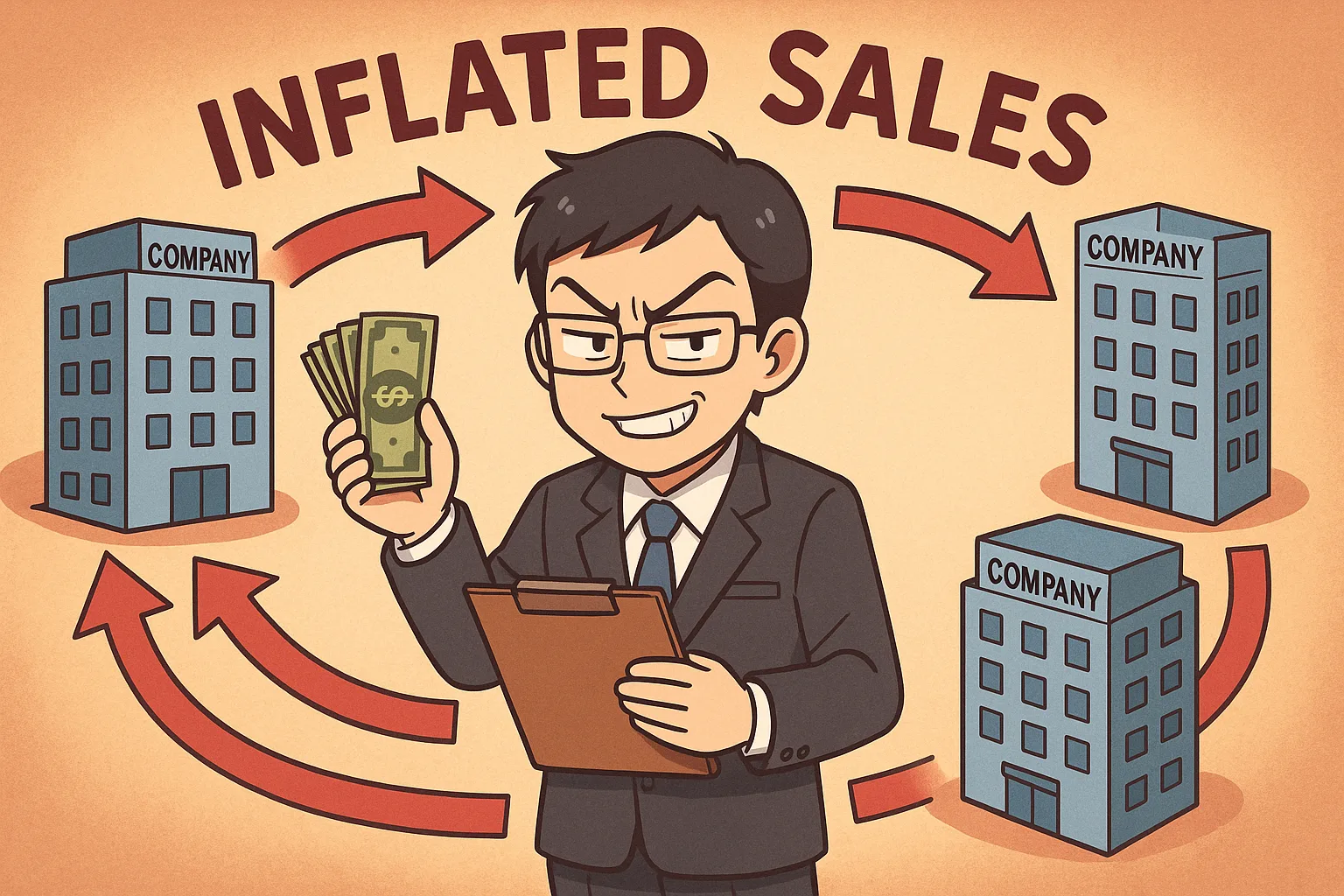
- 1. ニュース追記
- 2. 議事録AIとしてはPLAUDを活用しています。
- 3. 導入:急成長スタートアップに何が起きたのか?
- 4. オルツとは?AI議事録サービスで急成長した企業
- 5. 発覚した不祥事の内容:売上の最大9割水増しという現実
- 6. 不祥事発覚までの経緯:上場から一転、強制調査と暴露まで
- 7. 粉飾の手口:実態なき「循環取引」による売上かさ上げ
- 8. 不正の原因:成長至上主義とガバナンス欠如が生んだ落とし穴
- 9. 社内外の反応と影響:株価急落、信用失墜と広がる波紋
- 10. オルツの対応:調査報告・謝罪と再発防止策、そして再建への模索
- 11. 今後の見通し:信頼回復への道のりと再生の可能性
- 12. まとめ:急成長の代償と教訓
ニュース追記
10/9 AIスタートアップ「オルツ」粉飾決算の疑いで元社長と前社長ら4人逮捕 110億円超える架空の売上計上か
粉飾決算ってどんな時に逮捕されるの?
「金額の大小だけで逮捕されるかどうかは決まりません」。粉飾決算(=財務諸表の虚偽記載)は「故意に事実と異なる決算を作り、公表・提出したか」という行為の悪質性・影響範囲・意図の有無などによって判断されます。
| 適用法 | 主な対象 | 刑罰・罰則 |
|---|---|---|
| 金融商品取引法(193条・197条など) | 上場企業など、有価証券報告書の虚偽記載 | 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は7億円以下の罰金) |
| 会社法(970条・972条など) | 非上場会社でも虚偽の計算書類を作成・備置 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
| 法人税法・消費税法など | 虚偽申告による脱税 | 重加算税+刑事罰(10年以下の懲役など) |
過去の事例から言えば、数千万円〜数十億円規模の粉飾で逮捕に至るケースが多いです。ただし、「額が少ないから安全」ということはありません。とはいえ今回は110億円ですか。まあ逮捕なんでしょうね。
議事録AIとしてはPLAUDを活用しています。
循環取引で売上を水増ししているイラストを描いて頼んだら、上記イラストになりました。不正な販売?? それはさておき・・(^^;
AI議事録めっちゃ使っています。PLAUDを購入してます。以前も以下の記事にまとめました。
PLAUDの販売状況などを聞いてみました。
シリーズ累計出荷台数:2025年6月時点で 100万台以上。
売上実績:
- 「PLAUD NOTE」は累計で 120億円以上 の売上を達成 。
- 日本市場における売上は2024年1月比で 21倍増 し、PRイベントでは調達額も累計 5,400万ドル(約60億円以上) に達したとの報告があります。
従業員:2025年春時点では 400名超 に達しているとされています
PLAUDはアメリカの会社ですね。なかなかAIの大元の部分を作るのに今から日本の企業が追いつける気はしませんが、議事録AIアプリのような部分的なアプリならまだまだ日本企業にもチャンスが有るのかなあと思っていました。自分ではPLAUD買っておいてなんですが。オルツ社はAIの議事録をやっていることは知っていましたが、AI GIJIROKUってアプリ自体を見かけることもないし、使っている人にも会ったことがありません。一般の人向けに売っているのではなく、大きめの企業などにBtoBで販売してるから見かけないだけなのかと思っていました。ところが、今回の粉飾事件発生で、そもそも全然売れていないことが白日のもとにさらされてしまいましたね。
確かにAIの議事録だけでそんなに収益がたくさん出るのかは疑問に思っています。録音データさえあれば、文字起こし、ようやくはどの生成AIでもできるし、プロンプトの事前登録なども含めても生成AI間で差が出にくい気がします。ChatGPTやGemini、そしてCopilotが本腰を入れて取り組んだら、すぐ吹き飛ばされてしまう気もします。
ただPLAUDは録音のハードもあって、これがコンパクトでかわいい。しかし2.7万円とお高いですが。新しいもの好き、ガジェット好きが思わず買ってしまうような製品だからある程度売れているのでしょう。ただまあ、今後iPhoneで録音してそのまま要約というアプリが増えてきたら、ハードの優位性もどこまで残るかは疑問ではあります。
そんな中、今回の事件は起こりました。事件と言っていいでしょう。株式市場の信頼を揺るがす事件。それがありがちな循環取引で売上水増しだなんて、アホらしい限りです。これ以降はAI議事録スタートアップ「オルツ」で発覚した粉飾決算の実態を生成AIで確認しながら見ていきます。
導入:急成長スタートアップに何が起きたのか?
わずか創業数年で東証グロース市場に上場し、AI議事録サービス「AI GIJIROKU(ギジロク)」で注目を集めていたスタートアップ企業「オルツ」。革新的なパーソナル人工知能(P.A.I.)の開発や会議録自動作成ソフトの提供などで評価され、経産省のJ-Startupや日経「未来の市場をつくる100社」にも選出された期待の星でした。しかし、そのオルツで売上の最大9割に及ぶ架空計上という衝撃的な不祥事が明るみに出たのです。上場からわずか半年で株価はピークの4分の1に暴落し、ついには法的整理に追い込まれる事態となりました。本記事では、この粉飾決算事件の内容と発覚までの経緯、巧妙に見えた手口の実態、社内外への影響、そしてオルツの対応と今後の行方について、一般の方にもわかりやすく解説します。
オルツとは?AI議事録サービスで急成長した企業
オルツ(株式会社オルツ)は2014年創業のAI開発スタートアップです。社名は英語で「alt(代替)」を意味し、「全人類に一人一つのパーソナルAIを」という壮大なビジョンを掲げていました。主力製品は会議や打ち合わせの音声を自動文字起こし・要約する**AI議事録サービス「AI GIJIROKU」で、2020年に発売されて以降急速にユーザー企業を増やしてきました。実際、2024年末時点で有料アカウント数は約2万8千件、導入企業数は9,000社を突破したと発表していました。このAI議事録事業がオルツの売上の約93%**を占める中核となっており、同社はAIブームの追い風も受けて急成長。「5年で時価総額1兆円も視野」といった触れ込みで2024年10月には東証グロース市場に華々しく上場を果たします。
しかし、この成功ストーリーの裏側で、後に売上の大部分が架空だった疑いが浮上することになります。主力商品AI GIJIROKUによる売上成長には陰りが見えず、むしろ不自然なほど順調でした。その秘密が何だったのか
発覚した不祥事の内容:売上の最大9割水増しという現実
2025年4月、オルツに関する驚くべき疑惑が表面化しました。同社の売上高の大半が架空ではないかというものです。実態のない有料アカウントが多数見つかり、売上の4~5割を特定の1社の提携先に依存していたことから、不自然な取引の存在が疑われました。関係者の話として、上場直後の2024年12月期決算(売上約60億円)のうち7割にあたる約40億円が水増しされていた可能性が指摘され、社内の一部では「売上の95%は虚偽ではないか」という声すら上がっていたのです。
第三者委員会の報告によれば、オルツは2021年12月期から2024年12月期までの4年間にわたり売上を不正に過大計上していました。その総額は累計119億円にも上り、各期の売上高の8~9割近くを占める年もあったといいます。これは単なる経理ミスではなく、意図的かつ組織的な粉飾決算でした。オルツの主力事業であるAI議事録サービスの売上を中心に、ほぼ会社全体の業績が虚構で塗り固められていたことになります。
この不正により、帳簿上は急成長を遂げているように見えていたオルツですが、実態は大部分の取引に裏付けがなかったのです。では、なぜ長期間にわたりこれほど大規模な粉飾が行われ、発覚しなかったのか——その経緯を振り返ってみましょう。
不祥事発覚までの経緯:上場から一転、強制調査と暴露まで
上場から半年余りが過ぎた2025年4月初旬、事態は急変します。金融当局である**証券取引等監視委員会(SESC)**がオルツに対し立ち入り検査を行い、AI議事録サービス「AI GIJIROKU」の売上に実態のない過大計上がある疑いが浮上しました。この強制調査により不正の可能性を把握したオルツは、4月25日付で第三者委員会による調査を実施することを公表し、社外の専門家による徹底的な検証に乗り出します。
一方、この直前から元社員による内部告発もインターネット上で注目を集めていました。営業を担当していた元従業員が匿名で暴露したところによれば、「請求書や入金の詳細が確認できない」「契約者リストの提出に1週間もかかる」など社内管理体制の杜撰さが指摘され、極めつけに「売上の95%は嘘ではないか」という衝撃的な告発内容でした。この内部告発はSNSやネット記事で拡散され、オルツに対する疑念が一気に高まるきっかけともなりました。
第三者委員会の調査は数ヶ月に及び、2025年7月末に報告書が取りまとめられます。そして7月28日、オルツは調査結果を公表し、自社の不正会計を公式に認める内容を明らかにしました。同日付で創業者である米倉千貴CEOが代表取締役を辞任し、経営トップ自ら引責の形となります。さらに追い打ちをかけるように、オルツは7月30日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請しました。負債総額は約24億円にも達し、自力での債務返済や再建が困難と判断したための措置です。東京証券取引所も同日、上場企業としての信頼を失墜させた事態を重く見て、オルツ株を8月31日付で上場廃止とする決定を下しました。
こうして、わずか10ヶ月前には上場の鐘を鳴らしていたベンチャー企業が、一転して市場から姿を消すことが事実上決まったのです。では、肝心の粉飾の手口とはどのようなものだったのでしょうか。その巧妙さと実態について見ていきましょう。
粉飾の手口:実態なき「循環取引」による売上かさ上げ
オルツが行っていたとされる「SPスキーム」の概念図。不正取引の構造は驚くほど単純な循環取引でした。オルツは自社のAI議事録ライセンスを販売パートナー経由で提供していましたが、特に「スーパーパートナー(SP)」と呼ばれる一部代理店に対しては、ライセンスを大量一括販売した時点で売上を計上していたのです。しかし調査報告書によれば、このSPに対するライセンス販売には実態が伴っていませんでした。オルツからSPに「○件のアカウント発行依頼」を出した記録こそあるものの、実際にはSPにライセンスが発行された形跡がなく、エンドユーザーへの提供や利用も行われていなかったのです。
では、売上代金はどこから来たのかというと、そこに絡んでいたのが広告代理店や研究開発委託先でした。オルツはまず複数の広告代理店(報告書上はA社、Q社、O社、N社)に巨額の「広告宣伝費」を支出し、あるいは特定の開発会社(X社、Y社など)に「研究開発費」を支払いました。しかしこれらの支出は名目のみで、実際には十分な広告や開発業務の実態がないまま資金が社外に流出します。そして流出した資金は広告代理店経由でSPに渡され、最終的にSPからオルツへとライセンス購入代金として還流してきました。こうしてオルツ自ら拠出した資金が一回りして売上として戻ってくる仕組みが作られていたのです。要するに、自社のお金をぐるっと回して帳簿上の売上高を水増しする「マッチポンプ」のような手口であり、第三者委員会も「典型的な循環取引に他ならない」と結論づけています。
この不正スキームは2021年6月頃から2025年3月まで長期間にわたって継続されていました。当初は売上先(SP)と外注先が同一で金額も同額という単純な構図であったため、監査法人から「これは売上計上と認められない」と指摘を受けたといいます。そこでオルツ側は手口を“進化”させ、関与する代理店やSPの数を増やしたり、取引のタイミングをずらしたりして手繰りにくく工夫しました。監査法人に循環取引を疑われて以降は、広告代理店を一社に一本化する代わりに研究開発費名目での資金循環も新たに加え、広告費ばかりが膨らんで怪しまれないよう調整していたのです。社内では資金の流れを管理するため「代理店事務フロー(後にSP_事務フローと改称)」と題したGoogleスプレッドシートまで用いて細かく資金移動を追跡していたことも判明しました。
このように、見かけ上は複数社との正常な取引に装いつつ、裏では自社資金をぐるぐる回して売上高を捏造するという仕組みだったわけです。皮肉なことに、その構造自体は極めてシンプルであり、ある意味“バレやすい”やり方とも言えます。それでも長年発覚しなかった背景には、次に述べるような経営陣の姿勢や内部統制の問題が横たわっていました。
不正の原因:成長至上主義とガバナンス欠如が生んだ落とし穴
第三者委員会の報告書は、今回の不正の根本原因は経営トップ層の「誠実性」の欠如にあると厳しく指摘しています。創業者でCEOであった米倉氏をはじめ、取締役CFO、財務経理部長、事業部長など複数の経営幹部が深く関与して不正スキームを形成・実行していたことが明らかになりました。彼ら経営陣は「売上高10億円」など高すぎる目標を掲げて業績拡大と新規上場を強烈に志向し、そのプレッシャーがコンプライアンス軽視の企業風土を醸成したと報告書は分析しています。要するに、「とにかく数字を伸ばせ、上場を果たせ」が最優先で、倫理や法遵守は二の次という空気が社内に蔓延していたのです。
内部統制面でも問題が山積していました。まず牽制機能の欠如です。営業など担当部門や管理部門によるチェックが働かず、内部監査も機能不全に陥っていました。さらに社外取締役や監査役といった本来ブレーキ役となるべき人たちも限界があり、十分に不正を防止できませんでした。実際、元社外取締役の一人は「この会社はガバナンスが機能していない」と嘆いていたとも伝えられています。人材面でも、CEOやCFOの周囲は「イエスマンばかり」で固められ、組織として健全な意見具申やブレーキが利かない状態でした。
また、外部環境の要因も指摘されています。AIという最先端分野のベンチャー企業ということで周囲の期待値が高く、監査法人や投資家、取引所なども「この会社なら大丈夫だろう」と過度に信用してしまった可能性があります。オルツ自身も監査法人や大口株主であるVC(ベンチャーキャピタル)、上場時の主幹事証券会社などに対し、有料アカウント数や代理店での販売フロー、巨額の広告宣伝費の使途について虚偽の説明を繰り返し行っており、外部の目を巧みに欺いていました。創業者によるカリスマ性や「AIで世界を変える」という大義名分があったことで、誰もが深く突っ込めない雰囲気があったのかもしれません。
こうした内と外のチェック機能の不備が重なり、不正はエスカレートしていきました。結果として、企業統治(ガバナンス)の土台が脆弱なまま急成長してしまったことが、今回の粉飾決算の背景にあるといえます。
社内外の反応と影響:株価急落、信用失墜と広がる波紋
不正会計の発覚により、オルツは社内外で大きな混乱と影響を巻き起こしました。
社内の反応: 上述のように元社員による告発があったことからも分かるように、社内では以前から一部に疑念を抱く声があったようです。しかし実際に不正が公になったことで、多くの従業員はショックを受けたに違いありません。経営トップであるCEO自らが辞任に追い込まれ、CFO以下関与が疑われる幹部も責任を問われるのは必至です。上場企業の一員として誇りを持って働いていた社員たちは、一転して自社が粉飾決算企業の烙印を押される事態に直面し、動揺や失望は計り知れません。中には将来を悲観して退職する人や、士気を喪失する社員も出たことでしょう。
社外の反応: 投資家や市場からの信頼も崩壊しました。IPO時には「AIスタートアップの雄」ともてはやされたオルツですが、不正疑惑報道後は株価が急落。発覚前に比べ株価はわずか数ヶ月で4分の1近くまで暴落し、時価総額は泡と消えました。多くの株主、とりわけ上場時に参加した個人投資家は大きな損失を被り、ベンチャーに賭けたVCや金融機関にとっても痛手となりました。また、顧客企業にとっても「導入しているサービスの提供元が粉飾をしていた」となればイメージは悪く、不安や不信感を抱く要因になります。実際にサービスそのものの品質に問題がなかったとしても、企業への信用が揺らげば契約継続にも支障を来しかねません。
社会的にも大きな波紋が広がりました。AIブームの立役者と目されていたスタートアップが不正に手を染めていた事実は、メディアでも連日報道され、人々の驚きと落胆を呼びました。監督官庁や東京証券取引所は速やかに対応し、上場廃止や再発防止策の指導など厳しい姿勢を示しています。金融当局も金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの容疑で捜査を進めているとみられ、今後経営陣への法的責任追及が行われる可能性があります。また、この事件は他のスタートアップや投資家にも影響を与え、「急成長企業であってもガバナンスやコンプライアンスを軽視すればこうなる」という教訓として受け止められています。スタートアップ業界全体への信頼感を損ねる懸念もあり、健全なエコシステム構築のために再発防止への取り組みが求められています。
オルツの対応:調査報告・謝罪と再発防止策、そして再建への模索
不正発覚後、オルツは事態の収拾と信頼回復に向けて動き出しました。まず4月の時点で第三者委員会を設置して調査を開始し、社内の資料提出や関係者ヒアリングなど全面協力する姿勢を示しました。調査結果が判明した7月28日には、オルツは速やかに調査報告書を公表し、不正の事実を認めるプレスリリースを発出。同時に「関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪の意を表明し、社会的信用を裏切ったことへの反省を述べました(※報告書公表時のリリース内容より)。
経営責任の明確化も図られました。前述の通り米倉社長は7月28日付で辞任し、新たに日置友輔氏が代表取締役社長兼CFOに就任しています(同氏はそれまで財務責任者だった人物です)。関与が疑われる他の幹部についても、今後の調査結果次第では処分や退任が行われる見通しです。社内的にはコンプライアンス徹底と企業風土の改革に乗り出す構えで、従業員向け説明会や研修の実施、内部通報制度の強化などが検討されています。
第三者委員会から提言された再発防止策も公表されました。その柱は以下の通りです:
- 抜本的な組織改革・経営改革の実施: 権限の集中を改め、ガバナンス体制を強化する組織再編を行う
- 経営トップに対する牽制機能の強化: 社外取締役・監査役の独立性と機能強化、内部監査や内部通報制度の拡充、リスク管理委員会の改善など
- 内部統制機能と権限の見直し: 部門ごとの職務分掌を明確化し、お互いを牽制できる仕組みを導入する
- 企業風土の改善: 会計リテラシー向上の研修やモニタリング強化、経営理念・行動規範の見直しによって倫理観を醸成する
- 監査法人とのコミュニケーション強化: 外部監査人と十分に意思疎通し、疑問点は速やかに是正する体制づくり
これらを確実に実施し、二度と不正を起こさない企業へ生まれ変わることを目指すとしています。しかし皮肉にも、オルツは上場廃止と事実上の経営破綻という状態に至っており、自力で再発防止策を講じていくだけの体力は残されていません。そこで同社が選択したのが民事再生手続きによる再建でした。
7月30日に民事再生法の適用を申請したオルツは、裁判所の下で債務の整理と事業再生を進めることになります。具体的にはスポンサー企業を募り、事業譲渡による継続を模索する方針です。既にいくつかの企業や投資ファンドが名乗りを上げているとの報道もあり(※報道ベース)、今後スポンサーが決定すれば、オルツのAI議事録事業は別主体の下で引き継がれる可能性があります。その場合、経営陣を刷新しガバナンス体制を強化した上で事業継続を図ることになるでしょう。オルツ自身も「事業は止めず継続していく」とコメントを出しておりj、ユーザーへのサービス提供は維持しながら信頼回復に努める構えです。
今後の見通し:信頼回復への道のりと再生の可能性
信頼回復は険しい道となるでしょう。オルツの名前は今回の事件で大きく傷つき、「AI業界のエンロン」「計画倒産ではないか」など辛辣な声も一部では上がっています。上場企業として一度失った信用を取り戻すのは容易ではなく、たとえ事業がスポンサーに引き継がれてもブランド名の変更や徹底的な経営刷新が避けられません。ユーザー企業やパートナー企業に対しては、一から説明責任を果たし続ける努力が必要ですし、新たな顧客開拓や市場拡大は当面難航する可能性があります。
上場・資金調達面への影響も甚大です。既に東証グロース市場からの上場廃止が決まり、株式市場での資金調達の道は閉ざされました。今後再上場を目指すにしても、まずは債務整理とスポンサー支援による再建が前提となります。仮にスポンサー企業の傘下に入った場合は、非上場の事業子会社として再スタートを切る形も考えられます。その際には親会社からの資金提供を受けつつ、一定期間地道に信頼を積み重ねていくしかありません。また今回の件で、VCなど投資家のスタートアップを見る目も厳しくなるでしょう。「数字が良すぎる企業には裏があるかもしれない」という教訓が生まれ、デューデリジェンス(投資前調査)や監査の目が一段と光るようになると考えられます。短期的には、他のスタートアップが資金調達を行う際にも投資家からより詳細な説明を求められるなど、業界全体への影響も避けられないでしょう。
一方で、技術や事業そのものの価値までゼロになったわけではありません。AI議事録サービス自体には一定のニーズがあり、既存ユーザーも存在します。スポンサー企業が適切にテコ入れを行い、信頼できる体制でサービスを提供し続ければ、時間はかかっても再評価される余地は残されています。ただし競合も多い分野だけに、今回失った信用を差し引いてもなお顧客が選ぶ魅力を示せるかが課題です。
今回の事件は、「成長最優先」「とにかく上場」という風潮への警鐘でもあります。スタートアップにとってスピードや規模拡大は重要ですが、それ以上に足元を固める経営の健全性が不可欠です。オルツのケースでは、監査法人・取引所・投資家といった外部も含め誰も不正を止められなかった点で、日本のスタートアップ・エコシステム全体の課題が浮き彫りになりました。今後は業界を挙げてガバナンス強化に取り組み、信頼回復と再発防止に努めていく必要があります。
まとめ:急成長の代償と教訓
AI議事録企業オルツの粉飾決算事件は、急成長の陰に潜んだリスクが一気に顕在化した事例でした。数字上の成功に固執するあまり基本をおろそかにし、経営トップ自ら不正に手を染めたことで、会社も従業員も投資家も大きな代償を支払う結果となりました。かつて「未来のユニコーン候補」と期待されたベンチャーが、上場から1年足らずで経営破綻に陥った事実は、私たちに多くの教訓を残しています。
最大の教訓は、企業にとって信頼は何にも代えがたい財産だということです。不正によって得た一時の栄光は脆く、ひとたび信用を失えば事業継続すら危うくなります。また、どんな先端企業であってもガバナンスとコンプライアンス無しには持続的成長は望めないことを、本件は如実に示しました。投資家や監査人も含め、熱気に浮かれることなく冷静にリスクを見極める姿勢が求められます。
オルツの再生への道のりは平坦ではありませんが、今回の反省を活かし健全な経営体制の下で事業が再スタートできれば、再び社会に価値を提供できる可能性も残されています。何より、この痛ましい事件を業界全体で共有し、「第二のオルツ」を生まないための取り組みへ繋げていくことが重要です。スタートアップの夢と挑戦が健全な形で実現されるエコシステムを築くために、私たちもこの教訓を心に刻みたいと思います。
【参考資料】本記事は朝日新聞、ロイター通信、第三者委員会報告書の要旨および有識者の解説記事等をもとに作成しました。

