AIを活用して業務効率化落ちている?
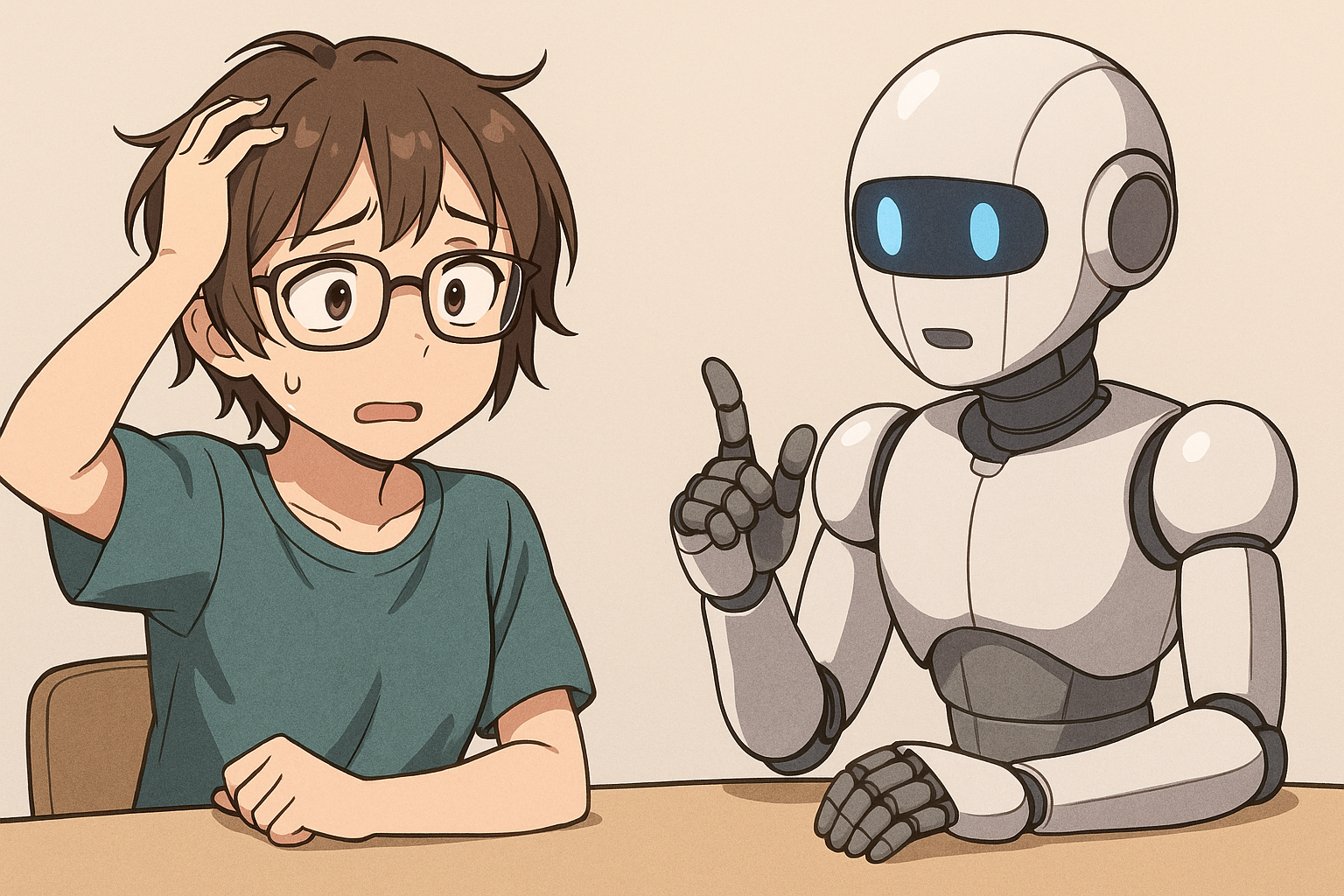
まず最初に、楽しく生成AIを活用している。毎日、何らかのAIを使っているし、この文章だって最後にはAIで校正をかけている。
とはいえ、日々新しい生成AIの機能が登場するので、どうしても検証に時間を取られてしまう。ここ数日も、ChatGPTエージェントが登場したと聞いて、「もう使えるようになったかな?」と確認しに行ってしまった。私のアカウント(PLUSプラン)では、まだ利用できないようだ。
検証が好きというのもあるが、それ以上に、生成AIに関するセミナーを多数実施しているという背景もある。セミナーで新しいネタを盛り込みたいので、つい色々と試してしまう。その結果、セミナー資料の枚数はどんどん増えていくわけだが。
以前の記事で、中小企業診断士による生成AIの使いどころをまとめた。その中で、自分の利用シーンも併せて紹介している。
生成AIにはたくさんの利用シーンがあり、少しずつ自分の仕事を楽にしてくれている気がする。いまだに多い紙での資料のやり取りも、生成AIでOCRをかけてしまえば気が楽だ。決算書もズレなく、正確にOCRできるようになったし、OCRのタイミングで経営指標まで計算してもらうこともできる。
ただ、ここから先は「効率化」という観点で怪しくなってくる。決算書を紙からエクセルに起こす作業自体は、間違いなく生成AIの方が速くて効率的だ。一方で、経営指標を出しても、それが本当に正しいかは現時点では自分で一つずつ計算して確認する必要がある。それなら最初から自分で計算したほうが早い、という話にもなる。
調査も同じだ。この業界について調べようと思えば、DeepResearchがさまざまな出典から情報を拾ってきてくれる。ざっくり業界を把握するだけなら、これ以上ないほどの高速化が実現できている。ただ、実際にレポートにまとめて資料として提出するとなると、そう簡単にはいかない。出典の一つひとつを確認し、生成AIが要約した内容が正しいか精査しないといけない。
その資料を説明するのは最終的に自分なので、内容はすべて理解しておかなければならない。
結果的に、以前は検索で数件の資料からまとめていた作業が、今では生成AIのおかげで数十件分の情報からまとめられるようになり、調査の精度は向上しているはずだ。ただ、その分、自分の作業時間はむしろ長くなっている。
もちろん、生成AIの出力は私が確認しなくても正しいのかもしれない。私自身が理解していなくても、質問があればまたAIに聞けばいいだけなのかもしれない。でも、そこまではまだ割り切れない。もし本当にそこまで任せるのであれば、私自身はもう必要なくなるからだ。
生成AIによって仕事がなくなっていく分野は、これからますます増えていくだろう。でも、自分に依頼されている仕事に関しては、元資料を確認し、理解し続けていかないといけない。
……この仕事、いつまで続けられるのだろうか。
そんなところで

